企業と学生の“ちょっといい関係”をつくるには?
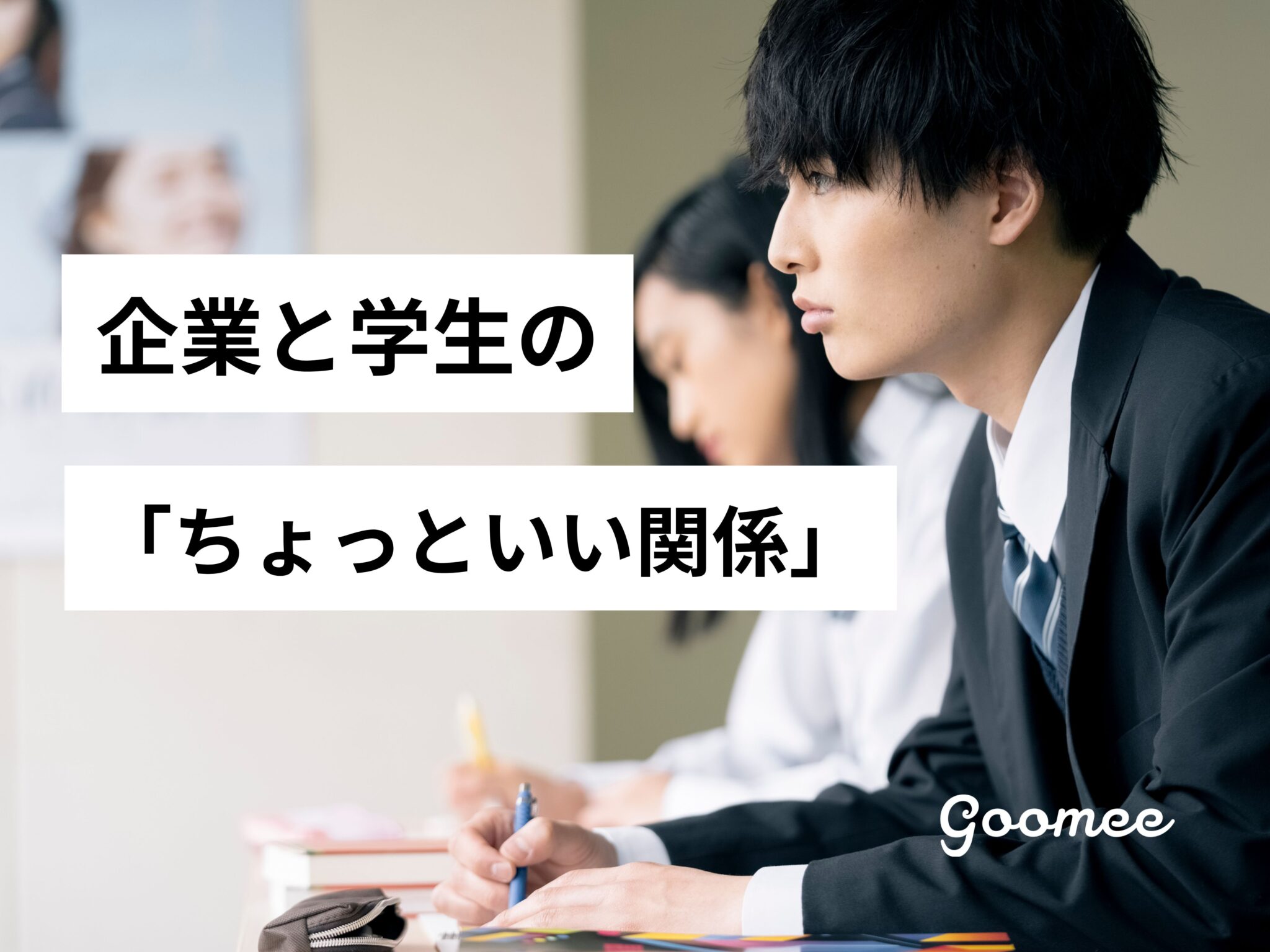

2024年1月の記事に掲載していただいた尼崎市武庫之荘の児童ホーム(学童)こども基地arika 代表の若松です!
その後arikaと同じ場所で、オルタナティブスクール“ここも”を開校する運びとなり、約1年が経ちました。
今回、
1.オルタナティブスクールとは
2.開校するに至った想い
3.”ここも”はこんなスクール
4 “ここも”でやっていきたいこと
このようなことを、ぜひみなさんに知っていただけたらと思います。
オルタナティブとは、「代わりの」という意味の英語です。
法制による定義はありませんが、既存の学校に合わない子どもたちのための、もうひとつの学校です。
「フリースクール」と称する学校もありますが、居場所要素が強いのがフリースクール、オルタナティブスクールは既存の学校の代わりに学ぶところ、というコンセプトが多いようです。
文科省によると、学校に行かなくなったこどもたちは11年連続で増加、直近では小中学生34万人が不登校という状況が報告されています。
2022年に児童ホーム(学童)とコミュニティスペースarikaをオープン以後も、こどもの関わりについて講座や書籍などで学んできました。
そんな中で2023年の秋からは、神戸のオルタナティブスクールで、週1回働く機会をいただくことになりました。
オルタナティブスクールのパイオニア“ラーンネットグローバルスクール”二校目の小学部で、“ラーンネットあーる”といいます。
“あーる”では、こどもをよく観察すること、言動を尊重し見守ることを具体的に学び、「こういう場所こそ、今必要なんだ!」との想いを強くしました。
また私自身の個性や得意なことも再認識でき、とてもありがたい経験をさせていただきました。
そんな中、ラーンネットに入学希望しても、定員超過のため通えない子がたくさんいると知り、『スクールは、まだまだ足りないんだ』と実感しました。
そのとき思い出したのは、うちの児童ホームarikaに来てくれていた不登校のAさんの姿でした。
arikaに通うようになって初めの頃は、人見知り、特にこどもに対してひどく緊張していました。
また、遊びでも初めてのことや前にうまくいかなかったことに対して、とても消極的でした。
それがだんだん、初めて会う子ともほどなくして打ち解けられるようになったり、意欲的になったりしてきたのです。
こどもの言動に対して、受容的・肯定的な関わりをすることで、安心して素の自分を出せるようになっていきます。
そのうちに、備わっている力がするすると出てきます。
そんな中で友達や大人から影響を受けることができるようになり、反対にその子が周りに影響を与えて貢献欲求も満たし、苦手意識や失敗への恐れ、不安が減り、気持ちの切り替えが上手くなっていきました。
そのことを思い返すに、arikaでも少なからず、学校が合わない子や保護者さまのお役に立てるのではないか、お役に立ちたい!と考えるようになりました。
また、その時期に、尼崎市の不登校対策が手厚くなる計画が発表になりました。
フリースクール等に通うお子さんの学費補助が予算に盛り込まれたのです。
その状況も背中を押してくれました。
(“ここも”の名前は、学校もいいけど「ココも、有りか!(ここも/arika)」という言葉遊びから生まれました。)
受容的・肯定的な関わり
まずは関わり方を大切にしています。その子のペースや意思、習熟度になるべく合わせながらも、全体を進めています。
学び方
遊びや体験、生活の中から、興味関心を深めたり広げたりしながら楽しんで学んでいきます。
そして、「みつめる」「たかめる」「つながる」を合言葉に、非認知能力*を伸ばすことをめざしています。
具体的なプログラムとしては、以下の内容を組み合わせて取り組んでいます。
[基礎学習]
自宅から持参した国語・算数の教材を各自で取組み
[体操]
動画に合わせて体操
[ここもミーティング]
朝と帰りに、こどもたちの調子や予定の共有とふりかえり
[Myタイム]
こどもたちがそれぞれ、自分がしたいことを取り組む
自由工作、手芸、レゴ、即興劇、パズル、人生ゲームなど
[プロジェクト学習(2024年度)]
Zine(小冊子)づくり、コマ回し・障がい者理解・さつまいも収穫・
宝探し・植物栽培・おもちつき・折り紙ドミノ・行事の内容を計画準備
[ランチ(スイーツ)クッキング]
月一回、みんなでメニューを考え買い物、調理、片付け
[フィールドワーク(2024年度)]
公園、図書館、鉱物カフェ見学、キッズプラザ大阪、王子動物園等
ほかに[読書] [手仕事]など
*非認知能力とは
テストや偏差値など数値で測定できる学力等が認知能力であるのに対して、目標達成に向かう意欲・自己肯定感や自制心・周りとの協働など、数値での測定が難しい能力は非認知能力と言われています。
カリキュラムの考え方
9時から14時の5時間の中で、基本的にその日のタイムテーブルに沿って過ごします。
MYタイムとして個々の裁量に任せる時間をゆったり設けていますが、こちらから提供するプログラムもあります。
全体の時間でも、なるべく個々に決定権をもてるようにしています。
こどもの力の引き出し方について
内発的動機づけも、外発的動機づけも、あるいは探究学習も基礎学力の習得等、個々も全体も…その子の今の成長段階に合わせて両方を使い分けたりするなど、相対するようなアプローチやコンテンツのいずれも大切にしています。
開かれた場のオリジナリティ
同じスペースで別の時間帯に児童ホーム・コミュニティスペースを運営しているため、老若男女、学校に行っているこどもたち、様々なプロフィールの大人たち、またいろんな機会との出会いが数多くあるのも特色です。
地域や実業のみなさんとの接点もたくさんあります。
ここもでは、こどもたちが自分の幸せをつかみとっていく大人になってほしい、と考えています。いずれ自立して主体的に生きる社会人になるには、さまざまな非認知能力を育んでいくことが不可欠です。
その力を発揮して幸せになっていくことは、決して一人ではできないことだと思います。
友達が困ったときに助けること、励ますこと
頑張ってる友達や先輩に刺激を受けること
ひとりでは力が足りない時に、誰かと一緒に多くのこと大きなことをやりとげること
自分とは異なる人も互いに認め活かしあうことでクリエイティブな世界が生まれること
そんなことを思うと、世界中のみんなひとりひとりと仲良くまではいかなくても、お互いを尊重して認め合う社会を願わざるを得ません。
生身の人間の世界では、綺麗ごとではすまないことが少なからず出てきます。乗り越えることが困難に感じるような挫折、足がすくむような不安な状況、本心とは裏腹な態度に出会うこと、自分の価値が低いと感じてしまうときに虚勢を張る姿など…。
今後ますますAIの活用や自動化が進んでいく中で、時には弱い誰かや成長過程にある誰かを許したり愛したりする力が、実はキーポイントになってくるのではないかと考えています。
それは「自他とも」であり、せめてフラットに受け容れるということと捉えました。
不完全な自分や他人を認めて、そのうえで自他とも励ませる人が増えていったら、どんなに素敵な世界が待っているでしょうか!
また、変化が速く複雑で不確実性の高い時代を生きていくこどもたちには、決まった正解がないため、協調性の他にも、柔軟性や多様な視点、仮説思考などが求められていると言われています。
物事や事象、状況について、目に映っていることや既知のことだけでなく、背景やその後の展開といった流れを捉え類推したり仮説を立て検証したりする力をしっかり養う。
広い視野や高い視座から捉える力によって、課題解決に導いていく。
“ここも”でもそのような力が大切であることを伝え、徐々にそれらを伸ばす機会をつくっていきたいと思います。
さて、国の動きはどうでしょうか。
政府は第5期科学技術基本計画において、現代はSociety4.0と呼ばれる情報社会であると定義、次に目指すべきは、Society5.0「経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」であるとしました。
第6期の計画では「持続可能性と強靭性を備え国民の安全と安心を確保するとともに一人ひとりが多様な幸せを実現できる社会像に、『信頼』や『分かち合い』を重んじる我が国の伝統的価値観を重ねてSociety5.0の実現を目指す」と表現されています。
「人間中心の社会」「多様な幸せを実現できる」「『信頼』や『分かち合い』」
ここものめざすものも、そこにありました。
その理想を、目の前のこどもたちの未来につなげていくことが、スクールのめざすところです。
それを心に留めながらも大らかに、地域の皆さんとも一緒に取り組んでいきたいと思います。
ぜひみなさん、ご一緒に!